起源は見当がつかないくらい古い?・ネームタグ(名札)の歴史

ネームタグは、日本語でいえば「名札」です。身近なところでは、小学生の胸に付けるものなどがあります。しかし、ネームタグが表示するのは人の名前ばかりとは限らず、なんらかの情報を伝えるために文字や記号が書き込まれたものも「ネームタグ」に含まれます。このような「何かを表示した札」は、さまざまな用途に応じて多様で、長い歴史を持ちます。ネームタグの歴史を見てまいります。
Index
人はいつ「札(ふだ)」を使い始めたか

いろいろな「札」を思い浮かべて、時代をさかのぼってみます。小学生の名札。国会議員が「出席」を表示するために机の上に立てる名票。これは明治時代の帝国議会までさかのぼります。
江戸時代、たとえば将軍家への献上品には、品目と献上した人の名を記した札がそえられました。法の定めを公示する「お触れ」は高札に。
戦国時代では、いくさにおもむく侍たちは、首をとられても身元がわかるようにふところに名札を入れました。身体のどこかに「いれずみ」で名前を彫ることもあったようです。
飛鳥時代から数多の仏像が造られますが、その多くには製作者の名前や製作年、由来などを記した銘文がそえられました。紙に書くことが多かったのですが、木板に記したり彫ったりすることもありました。
飛鳥時代から平安時代までの遺跡からは、時として大量の「木簡(もっかん)」が出土します。官僚たちの口上のメモ、役所での決済伝票として、あるいは荷札として、さまざまな用途に使われたようです。
木の遺物が残りにくいほど昔のものでは、「金石文」、すなわち、金属や石に文字を刻んだものの中に、考えようによっては「札」と取れなくもないものがあります。
こうして考えてみますと、ほぼ、人が「文字」というものを持ったときから、石、鉄や青銅、紙、木材に書いたり刻んだりすることでなんらかの目印、徴表、情報伝達に役立ててきたものと思われます。
文字を持たない民族でも、なんらかの記号は用いているでしょうから、やはり「札」を使用することは可能だったはずです。
そうしますと、「札」というものの歴史は、ほとんど人類の発祥と同じ時期までさかのぼるとも言えます。
名札の本質的機能は「ID」

気が遠くなるほど大昔のことはさておいて、こんにちの「タグ」につながるイメージのものから見ていきましょう。
日本の歴史で言えば、古代の官僚が使った「名簿(みょうぶ・なづき)」または「名符(みょうふ)」です。自分の官位と姓名を書き記した名札でした。
現代のオフィスで使われるネームタグにも、建物の入館証、エレベーターや部屋に立ち入る際のチェックといった機能を兼ねそなえ、社員証としての性格を持つものがあります。古代の日本でも、まずは名札の持つ機能は「身分証明・ID」だったわけです。
主従関係の証しとして
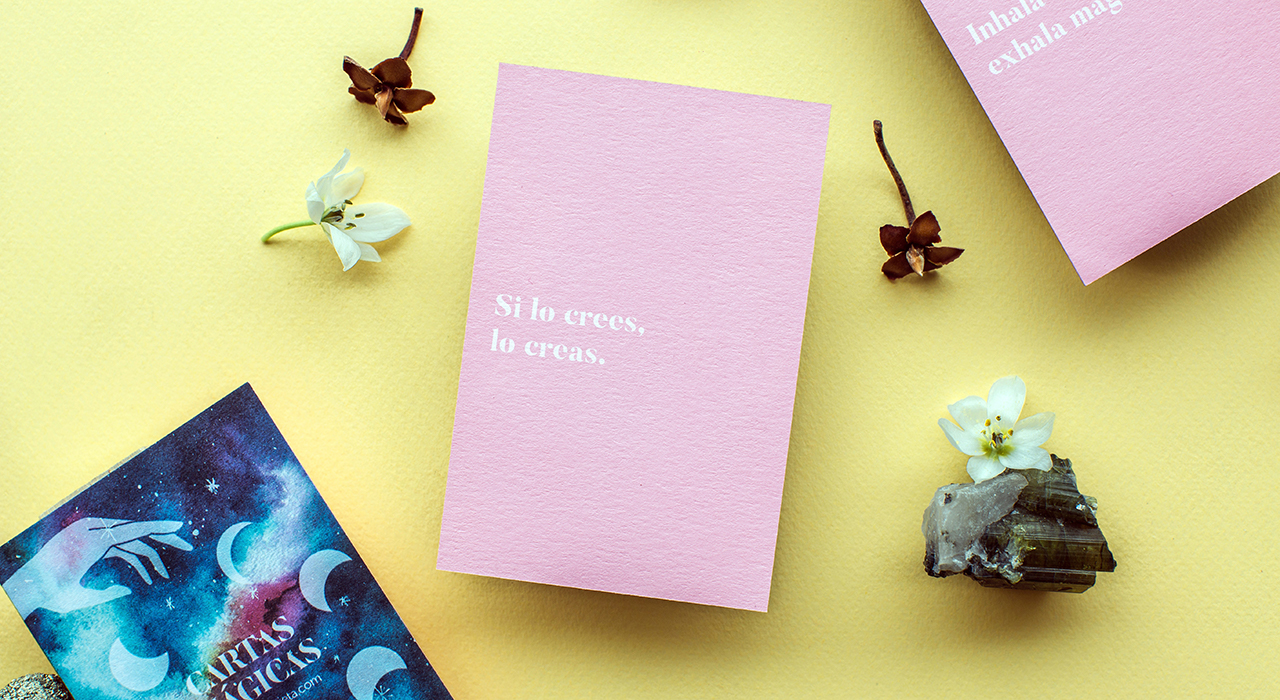
「名前」は、「言葉に霊が宿る」という言霊(ことだま)の考え方にもとづいて、単なる音声や記号ではなく、その存在そのものと同じくらいの重みがあるものと考えられました。今でも人の名前をおろそかにすることは失礼なことですが、呪術が今以上に信じられていた古代ではそうした思いはずっと強かったのです。
古代では、中下級の官僚が官途に就くにあたって、あらかじめ自分の姓名、官位、年月日などを記した名札を持参し、仕える相手の上司や主人に提出しました。このことには、上の考え方にもとづいて、自分の精神、肉体、身分をまるごと相手に捧げるという呪術的意味もあったのです。
のちの武家社会の時代でも、呪術的意味はややうすれましたが、名簿奉呈と見参、つまり名札・名簿の提出と「お目見え」が主従関係を結ぶにあたって不可欠の儀礼でした。
アジア太平洋戦争の頃に広がりを見せる

旧帝国陸軍の兵士は、野戦服の胸のあたりに所属部隊と氏名を記した布をワッペンのように縫いつけることがありました。
欧米の軍隊では、兵士の同定のためにしばしば2枚1組や1枚の金属板を2つに折るタイプの「認識票」が使われました。兵士が前線で戦死した際、2片のうちひとつを死体から外して持ち帰り、あとで死体を回収するときにその兵士が身につけているものと合わせて確認する方式です。
このような2枚式の認識票は、旧帝国軍では採用されていません。その代わりに、兵士は文字通り「名札」や、あるいはもっとシンプルに「番号札」を持って前線におもむきました。
一般民間人、学生への広がりも戦時中

1941年(昭和16年)に、小学校が「国民学校」に改組されました。これと同時に、小学生は服の上着の胸あたりに、布でできた名札を縫いつけるようになりました。
この時代、軍事教練や勤労動員などのため、軍人や軍需産業関係者が学校に入ってくることも多く、初めて見る子たちでも名前がわかると命令や動員がしやすくなることから、名札を付けるようになったようです。
学校だけでなく、一般の民間人にも名札を付ける習慣が広がります。男性は「国民服」の上着、胸のあたりに、女性はモンペの腰のあたりに名札を縫いつけました。
もちろん一般民間人も軍事教練や勤労動員の義務がありましたので、軍人や軍需産業関係者にとって名札には利便性があったのです。警察官や憲兵、住民相互による監視のためにも役立っていました。また、銃爆撃で亡くなった方の身元確認につながることもありました。
戦後、小学校で名札は継続
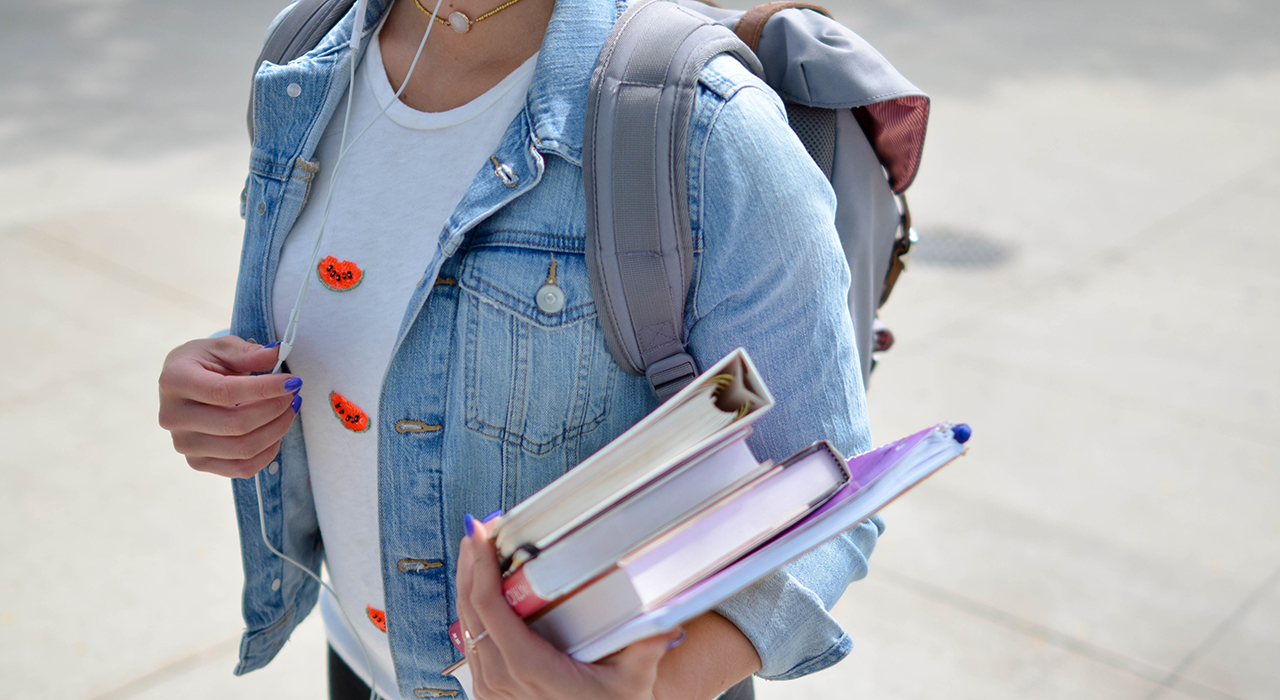
終戦後、大人は名札をつけなくなりましたが、小中学校では名札の使用は続きました。戦後しばらくの間、出産数が大きく増大したため、小中学校の生徒数が増え、1学年に数百人もいる学校も現れています。すると、担任するクラス以外の生徒の顔と名前を一致させるのは教員たちにとって至難の業となります。名札が必要でした。小学校1年生のクラスを受け持つ先生が、名札にひとりひとり生徒の名前を書くこともあったようです。
昭和の頃つかわれた名札は、学年、学級、名前を書いた紙をビニール製ケースに入れ、服に安全ピンで留めるタイプが主流でした。ビニールケースに10円玉を入れ、子どもが必要な時に公衆電話を使えるようにする保護者もいました。
防犯意識が高まる中で

昭和が終わり平成となる頃になると、誘拐などの犯罪に児童が巻き込まれることに対する懸念が広がってきました。名札が犯罪者に情報を与え、誘拐などの犯罪につながるのではないかとの不安が高まります。
そのため、名札の着用を校内だけにしたり、名札そのものを廃止したりする学校も出てきました。
2006年、「裏返せる名札」が登場します。安全ピンとビニールケースの間をつなぐプラスティックのパーツにくふうがあり、そこで名札を回転させることで、名前を記した面を裏返せるようになっているのです。
現代の「ネームタグ」は大きく進化

近年は、オフィスビルのセキュリティーのハイテク化にともなって、ネームタグにICチップが内蔵され、これが入り口ゲートの通行証、入構証の役割を果たすようなものが一般的になっています。こういったIC付きネームタグであればゲート通過を出退勤時刻の記録、つまりタイムカードの機能に利用することもできます。
このようなネームタグは、カードにしてケースに入れ、ストラップで首から下げるスタイルが多いです。カードに氏名や顔写真を入れることもあります。ただ、こういうものは社内だけ着用して、通勤の電車の中ではしまっておくのがふつうです。